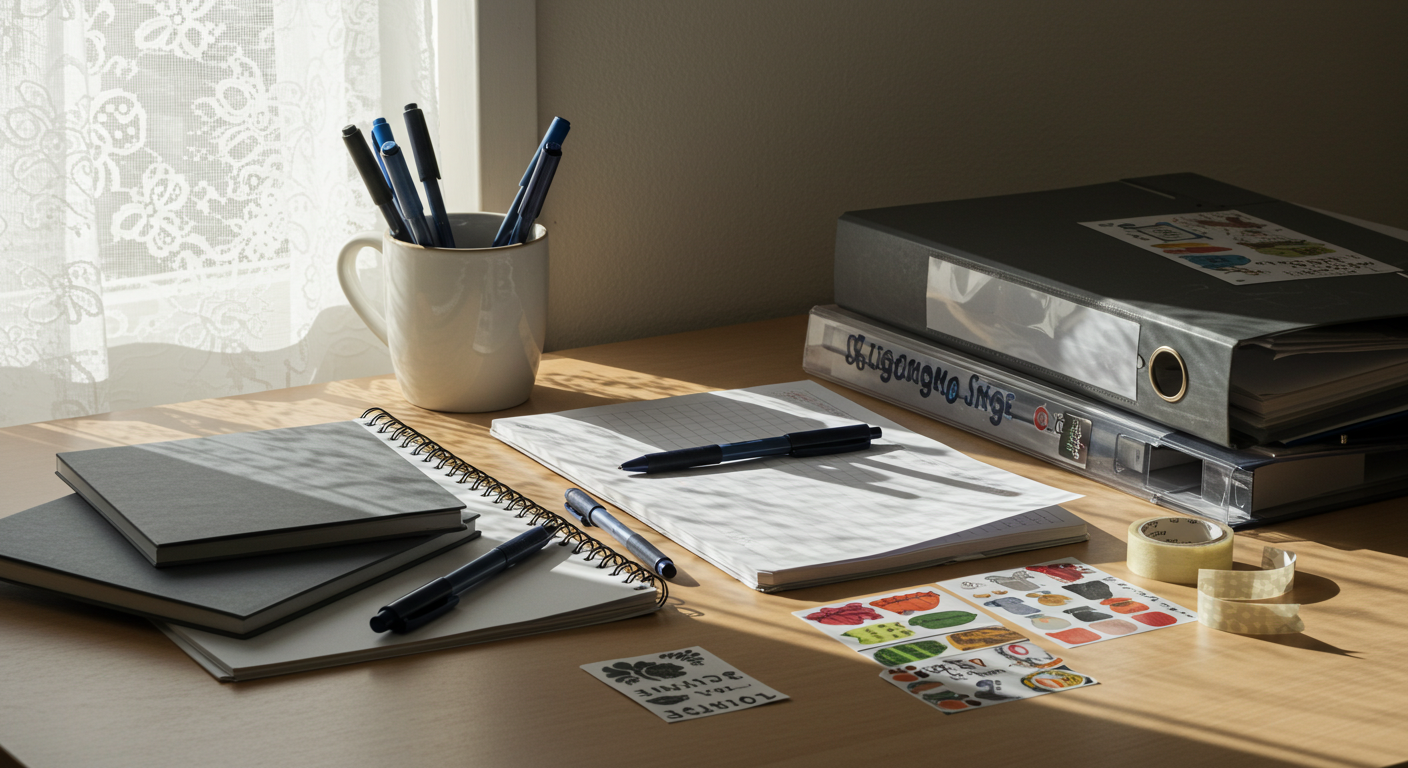墓じまいをすると祟り(たたり)や不幸が起こるのか?うそか本当か徹底解説

墓じまいで祟り(たたり)が起こる?
結論からいうと、
墓じまいを行ったからといって、祟りや不幸が起こるということはありません。
本当のところは「正しく供養すれば問題は起きない」というのが、僧侶や専門家の共通した見解です。
むしろ無縁墓※となり継承者がいなく、手入れされることなく放置される方が問題です。
墓じまいには正しい手順と心を込めた供養が大切であり、それを行えばご先祖を大切にする気持ちをきちんと伝えることができます。

※無縁墓(むえんぼ)とは、遺族や親族などお墓を管理・供養する人がいなくなり、誰からもお参りされなくなったお墓のことを指します。
もう少しわかりやすく言い換えると、「お墓を見守ってくれる人がいなくなり、放置された状態になったお墓」のことです。
墓じまいで祟りや不幸が起きたという話は本当?
墓じまいによって祟りや不幸が起こるという話には、科学的・宗教的な根拠はありません。
よくある体験談:「体調を崩した」「家族にトラブルがあった」
墓じまいを終えた後に、「急に体調を崩した」「家族が入院した」「身内と揉めた」など、何らかの出来事が起こったという声があります。また、親戚や知人から「それは祟りだ」と言われ、不安になってしまう方もいます。
これらの話を聞くと、「やっぱり墓じまいは良くないのでは…」と感じるのも無理はありません。
起きた出来事と墓じまいは、本当に関係しているのか?
墓じまいの直後に何らかの出来事が起こると、それを墓じまいと結びつけてしまうのは人の心理として自然な反応です。
しかし、実際には「たまたま時期が重なっただけ」に過ぎないのですが、墓じまい直後だったため、つい結びつけて考えてしまうことがあります。
これは人間が不安や後悔を感じたとき、それに理由を求めてしまう傾向があるからです。その結果、「あのとき墓じまいをしたからでは」と考えてしまうのです。
それらが本当に墓じまいと関係があるのか、冷静に見極めることが大切です。
供養を怠ると「祟り」と感じてしまう心のスキが生まれる
逆に、閉眼供養※などの手順を省いたまま墓じまいをしてしまうと、「本当に大丈夫だったのだろうか」という不安が心に残り、その不安が、ちょっとした体調不良や家庭内のトラブルと重なったとき、「これは墓じまいの祟りかもしれない」と感じてしまうのです。
心理的な不安が原因で、「祟り」や「不幸」といった出来事を結びつけてしまうことになるのです。

閉眼供養(へいがんくよう)とは、魂抜きとも言い、お墓や仏壇に宿っているとされるご先祖の魂を、お寺の僧侶に読経してもらい、感謝の気持ちとともに静かに送り出す儀式のことです。
わかりやすく言えば、
「ご先祖の魂に『ありがとうございました』と伝え、お墓や仏壇を片づける前に心を込めて見送る儀式」です。
専門家に聞く「墓じまいと祟り(たたり)」の関係
仏教では「死者が祟る(たたる)」という考え方はない
仏教の教えでは、亡くなった方が現世にとどまって祟るという考えは基本的に存在しません。
仏教の立場では、ご先祖や故人は祟る存在ではなく、極楽浄土に向かって旅立たれる尊い存在とされています。
そもそも祟りとは、古くは日本の神道や民間信仰の中で生まれた考えであり、仏教の葬送儀礼とは異なる背景を持ちます。
仏教における葬儀や法要は、故人の魂を静かに送るための儀式であり、災いを避けるために行うものではありません。
そのため、「墓じまいをすると祟りが起きる」という話は、仏教的に見ると根拠のないうそといえます。
墓じまいで祟りや不幸が起こることはない――それが専門家の共通した見解です
不安を感じるのは、ご先祖を大切に思っているからこそ
墓じまいにまつわる祟りや不幸の話に不安を感じてしまうのは、「ご先祖に申し訳ない」「粗末にしてしまうのでは」という気持ちがあるからでしょう。
ご先祖を粗末にしたくないという気持ちの表れなので、そのやさしさや敬意はとても尊いものだと思います。
けれど墓じまいは、あくまで生活環境や家族の事情に合わせた供養の見直しであり、ご先祖に対する愛情や敬意があるからこそ選ばれる行動です。
供養の形が変わるだけで、ご先祖を大切にする気持ちをなくすことにはなりません。
むしろ、無縁墓になる前に責任を持って整理することは、ご先祖を大切に思うがゆえといえるでしょう。
仏教の教えでは、墓じまいは正しい供養をすれば問題ない
僧侶や霊園関係者が口をそろえて伝えているのは、「墓じまいをするなら、正しい供養を行うことが何より大切」ということです。
仏教の立場では、ご先祖は供養されることを望んでおり、供養の形が変わること自体に問題はありません。
お墓に宿る魂をお寺のご住職により浄化し、新たな供養先へと心を込めて移していきます。
閉眼供養で安心して次の供養へつなぐ
墓じまいをする際には、「閉眼供養(へいがんくよう/たましいぬき)」という儀式を行います。これは仏教における大切な作法で、お墓に宿る魂をご僧侶により浄やかに抜いていただくものです。
この供養を行うことで、墓石はただの石となり、心を込めて新しい場所へご先祖をお迎えする準備が整います。
墓じまいを考え始めるきっかけは

そもそも墓じまいとは?
近年、墓じまいを検討する人が増えてきました。その背景には、少子高齢化や核家族化の影響があります。お墓を継ぐ人がいない家庭や、子どもが遠方に住んでいて管理が難しいという家庭が増え、「このままでは無縁墓になるかもしれない」という不安を抱える人も少なくありません。
あらためて知っておきたい基礎知識
墓じまいは、ご先祖への感謝と供養の気持ちを大切にしながら、現在の生活環境や家族の事情に合わせて供養の方法を見直す行為です。
今あるお墓からご遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を更地に戻し、管理者に返すことを指します。
これに加え、ご遺骨は新たな供養先へと移されるのが一般的で、この一連の流れは「改葬」と呼ばれています。
永代供養墓や納骨堂、樹木葬、散骨など、現代ではさまざまな選択肢が用意されており、それぞれの家族の事情に合った方法を選ぶことができます。
(こちらの記事もチェック)
お墓の管理が「今の暮らし」に合わなくなっている
高齢になってから故郷のお墓に通うのは、身体的にも経済的にも大きな負担になります。交通費や宿泊費、長時間の移動の疲労などが重なり、思うようにお参りできなくなることもあります。
また、お墓の維持費や清掃の手間を子どもに引き継がせることに心苦しさを感じ、墓じまいを決意する方も増えています。
「墓じまいは感謝の整理」と考えよう
供養の形は時代とともに変わっていくもの
墓じまいとは、従来のお墓を閉じて、遺骨を永代供養墓や納骨堂、樹木葬などに移すことであり、「供養をやめること」ではなく、「続けやすい形に変えること」です。
ご先祖への敬意や感謝の気持ちはきちんと込められています。
永代供養※や納骨堂も、立派な供養の場
近年では、子ども世代が遠方に住んでいる、お墓を継ぐ人がいない、という理由から、永代供養や納骨堂を選ぶ人が増えています。
これらの供養方法は、管理の手間や経済的な負担を減らしつつ、専門の寺院や施設が責任を持って供養してくれる点で安心感があります。
また、樹木葬など自然の中で眠る供養のかたちは、心にやさしく、現代的なライフスタイルにも合っていると評価されています。

※永代供養(えいたいくよう又はえいだいくよう)とは、家族や子孫に代わって、お寺や霊園が長い期間にわたり、故人の供養やお墓の管理をしてくれる供養の方法です。
わかりやすく言えば、
「お墓を守る人がいなくても、代わりにお寺が責任を持って供養を続けてくれる安心の仕組み」です。
墓じまい準備と流れ
家族や親族への説明は丁寧に、早めに行う
墓じまいは家族や親族の同意が不可欠なため、事前に話し合いの場を設けることが大切です。
なぜ墓じまいが必要なのか、例えば後継者がいないことや遠方で管理が難しい事情を伝えた上で、今後の供養方法や費用についても具体的に説明すると、理解を得やすくなります。
親族間のトラブル防止にも、できるだけ早い段階で相談することがよいでしょう。
お寺や霊園への相談と閉眼供養の依頼
墓じまいを決めたら、まずお墓の管理者であるお寺や霊園に早めに相談し、承諾を得る必要があります。
特に菩提寺※がある場合は、これまでの感謝を伝えつつ、改葬や墓じまいの理由を丁寧に説明しましょう。
墓石を撤去する前には僧侶に「閉眼供養(魂抜き)」を依頼します。これは遺骨を取り出す前に行うことが必須です。
閉眼供養の費用は3~5万円が目安ですが、地域や寺院によって異なりますので確認が必要です。

※菩提寺(ぼだいじ)とは、代々の家族やご先祖をお墓に納めたり、法事や供養をお願いしたりするために、特定の家が長く付き合っているお寺のことです。
わかりやすく言えば、
「その家のご先祖を供養してくれる“かかりつけのお寺”」のような存在です。
改葬許可申請や納骨先の手続きの流れ
改葬の手続きは法的にも決まっており、順序を守ることが重要です。
親族の同意を得る
新しい納骨先(永代供養墓や納骨堂、樹木葬など)を決める
墓地管理者やお寺に墓じまいの意思を伝え、承諾をもらう
自治体で「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入する。
今のお墓の「埋葬(納骨)証明書」、新しい納骨先の「受入証明書」、「改葬許可申請書」を自治体に提出する
「改葬許可証」が発行される。
「改葬許可証」取得後、閉眼供養を行い、遺骨を取り出す。
石材業者などに依頼して墓石の撤去や更地化を行う。
新しい納骨先へ遺骨を移し、必要に応じて開眼供養や納骨法要を行う。
不安を抱えたら専門家に早めに相談を
墓じまいは多くの手続きがあります。
自治体やお寺、専門業者に相談し、心穏やかに進めていけるようサポートを受けましょう。

実際に墓じまいを経験した人の声
墓じまいにまつわる「祟り」や「不幸」が本当に起こるのかと不安に思う方も多いですが、実際に墓じまいを経験した方々の声を聞くと、そうした心配はうそであることがよくわかります。
多くの方が「不幸はなかった」「むしろ心が軽くなった」と感じており、本当のところは墓じまいは安心して前に進める選択だといえます。
大変だった点:親族調整や手続きの煩雑さに苦労
墓じまいに伴う親族間の調整や説得に時間がかかったという声も多いです。
特に「ご先祖様に申し訳ない」と感じ、強く反対する親族を説得するのが一番の難関だったという経験談があります。
また、改葬許可申請やお寺・石材店とのやり取り、費用負担など、手続きの多さに戸惑う方も多くいました。
精神的にも「これでよかったのか」と葛藤したり、閉眼供養の際に寂しさや涙があふれたという話もあります。こうした苦労や心の揺れは自然なことです。今までの感謝の気持ちを胸に、新しい供養の形で、次のステージへと進みましょう。
良かった点:心がすっきりし、家族にも喜ばれた
「墓じまいをした後、特に不幸なことは起こらず、気持ちがとても楽になった」という声が多くあります。
遠方にあったお墓を整理して永代供養に移したことで、年に何度も通えないことへの罪悪感がなくなり、心が晴れやかになったと話す方もいます。
また、子どもが遠方に住んでいる家庭では、「子どもに負担をかけずに済む」と安心できたという感想も目立ちます。
おわりに。。
実際に墓じまいをした方の多くは、「祟りや不幸はなかった」と語り、むしろ心の重荷が軽くなったと感じています。
親族調整や手続きの煩雑さ、精神的な葛藤など大変な面はありますが、それ以上に「子どもに迷惑をかけたくない」「心がすっきりした」といった安心感と満足感が印象的です。
ご先祖への思いやりを大切にしながらも、自分たちの未来や暮らしを守るために、安心できる決断をしてください。
事前の準備と丁寧な話し合いを通じて、納得できる墓じまいを実現しましょう。正しい知識で安心して行動を起こせることを願っています。
ありがとうございました。