エンディングノートの作り方|50代おひとりさまが自分で手作りする方法
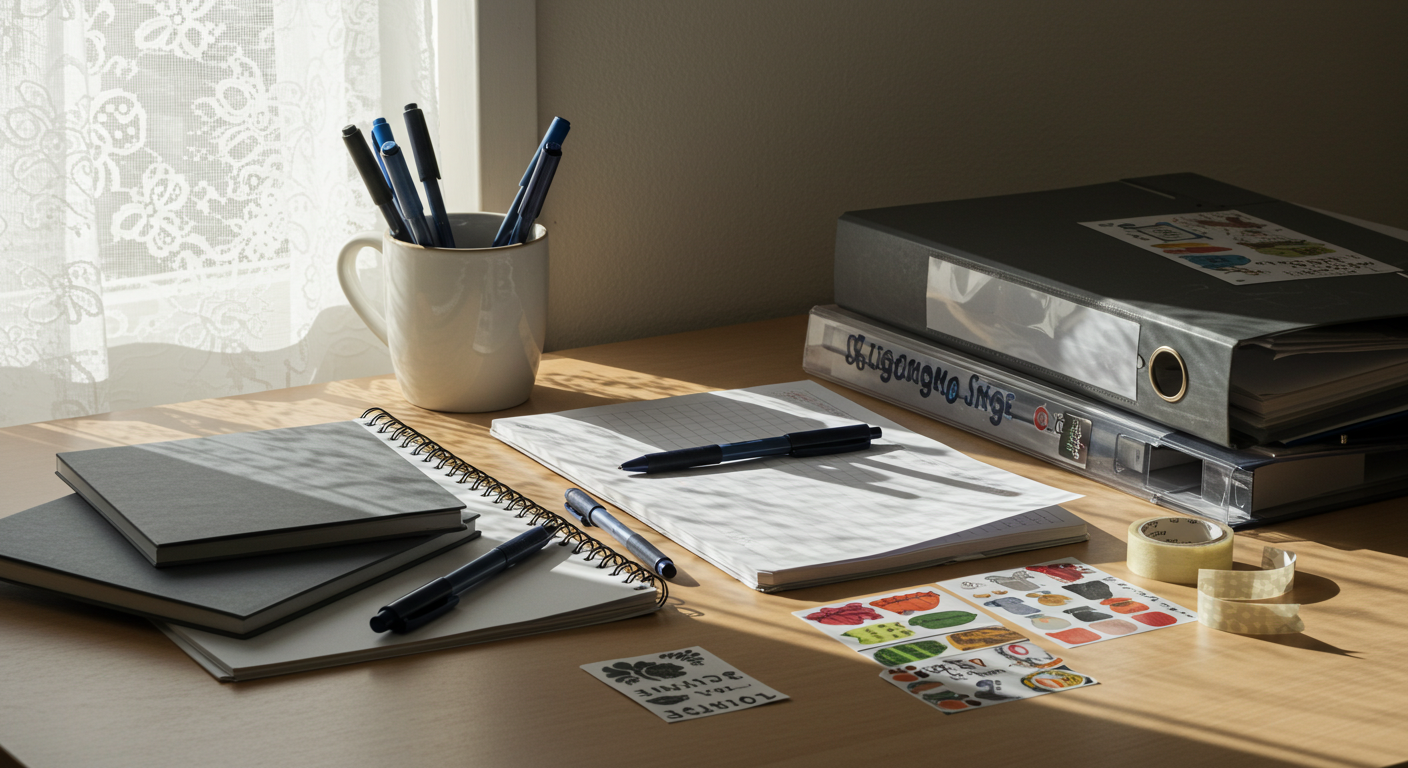
50代おひとりさまにとってエンディングノートの大切さ・基本知識
自分の意思を形にできるのは「今」
判断力や体力がしっかりしている今こそ、自分でエンディングノートを作るに適しています。50代は、日常生活に少し余裕が出てきて、自分の人生を振り返りながら、これからの暮らしを整えていける充実した時期です。さまざまな情報を集めることも可能な今こそ、エンディングノートを作る良い機会です。
周囲への思いやりをエンディングノートに込めて
おひとりさまの場合、万が一の際に手続きをお願いするのは親族や知人です。エンディングノートに必要な情報や希望を書き残しておけば、周囲の人が迷わずに動くことができ、負担がぐっと軽くなります。書いておくことで周囲の人に「何を望んでいたのか」を伝えることができ、家族間のトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。
エンディングノートは、形式やルールに縛られる必要はありません。自由に、手作りで、自分らしい作り方をすることができます。文字で残すことが難しい場合は、イラストやチェックリストでも構いません。必要なのは「自分の思いを伝えること」。
医療や介護に対する希望、財産の管理、そして葬儀についての考えなど、大切なことを自分の言葉で残すことができ、「自分のことは自分で決める」ことができます。
遺言書との違いを知って、上手に使い分けよう
エンディングノートは法的な効力はありません。自分の希望や想いを伝えることに特化したツールです。
財産や医療、介護のこと、葬儀についての希望など幅広く書くことができ、気持ちや生き方までも記せます。一方、遺言書は主に財産の分配について記す法的文書で、厳格な形式が求められます。必要に応じて遺言書と併用することで、備えとしてはより安心です。
おひとりさまにとって欠かせない理由とは?
おひとりさまが急な病気や事故で意思を伝えられなくなったとき、周囲の人が判断に困る場面は少なくありません。エンディングノートがあれば、医療や介護の希望、連絡してほしい人、財産の情報などが一目でわかるため、安心して対応を任せられます。手作りでも十分に機能し、必要な情報をまとめておくことで、行政や専門家が対応する際にもスムーズに進みます。
手作りのエンディングノートのもち味を活かす
エンディングノートの作り方には決まりがなく、思いついたことから自由に書き始められます。手作りならではの柔軟さがあり、決まった形式がないため、ノート1冊から始められ、自分らしいスタイルで記録できます。

手作りエンディングノートの作り方
ステップ1:準備するものをそろえよう
まずはエンディングノートを書くための道具を用意します。
ノートは大学ノートや白紙のもの、画用紙を使ったスクラップ風のものなど、好みに合わせて自由に選べます。ページを追加したい場合は、ルーズリーフやバインダーが便利です。
文字は見やすい黒や青のペンを使いましょう。
内容を整理しやすくするために、付箋やインデックスシールを使うのもおすすめです。
また、マスキングテープやシールを使えば、自分らしいデザインで楽しく作ることができます。
ステップ2:書いておきたい内容をリストアップ
エンディングノートには、自分に関するさまざまな情報を記録していきます。
1. どんな時に、誰に、何を伝えたいか
2. 医療や介護について、自分はどうされたい
3. 自分に関わる「お金」と「契約」の整理
4. 最期をどう迎えたいか
5. デジタル遺産についての整理
6. もしものときにペットや家のことはどうしたいか
7. 自分の気持ちや人生観をどう伝えたいか
ステップ3:書きやすいところから始めてみよう
最初からすべてを完璧に書こうとしなくても大丈夫です。
まずは、自分の名前や連絡先、親しい人の情報など、すぐに書ける内容からスタートしてみましょう。書きにくい項目は、無理に手をつける必要はありません。思いついたときに、少しずつページを増やしていくことで、自分らしいノートが自然にできあがっていきます。空欄があっても問題はなく、自由に書き直せるのが手作りエンディングノートの良さです。
ステップ4:見やすさと使いやすさを工夫しよう
どこに何が書いてあるかを把握しやすくするために、目次やインデックスを付けると便利です。内容を家族や信頼できる人と共有しておくことで、いざというときにも安心です。
さらに、自分らしさを出すために、写真やイラストを入れる、思い出の一言を添えるなど、表現の幅を広げてみましょう。
書いておきたい項目例(おひとりさまならではの視点で)
エンディングノートの作り方に正解はありませんが、書いておくと安心につながる項目はいくつかあります。
医療・介護についての希望
医療や介護に関する自分の考えを書いておくことで、いざという時に慌てずに済みます。延命治療を望むかどうか、など、自分の価値観を言葉にしておくことは大切です。
- 延命治療を望むかどうか
- リビングウィル(尊厳死の意思表示)の有無
- 臓器提供への考え
また、どのような介護を受けたいかという点も、おひとりさまにとって重要です。医療とあわせて介護についても書いておくと、まわりの人が判断ができ助かります。
- 介護はどこで、誰にしてもらいたいか
- 自宅での介護を希望するのか、施設を利用したいのか
- 介護にかけられる費用はいくらか
- 認知症や寝たきりになった場合の備えは?
緊急時や判断が難しいときの備え
判断能力が低下したときに備えて、誰に意思決定を託すかも明確にしておきましょう。任意後見契約を考えている場合は、その旨も記載しておくと安心です。
- 急な入院・事故・判断力の低下など、”自分で伝えられない場面”を想像する
- 緊急時の連絡先や、かかりつけ医の情報
- 連絡をとってほしい人、助けをお願いしたい人は誰か
- 誰に何を託したいか、どこまで任せたいか
葬儀やお墓のこと
自分らしい旅立ちを叶えるための情報も自分で選んでおくと気持ちが楽になります。残された人への負担を減らすために準備しておいたことなどあれば記載します。
- 葬儀の有無・形式(家族葬、無宗教、無葬など)
- 希望する宗教の有無
- お墓・納骨・供養の方法(永代供養、樹木葬、散骨など)
- 葬儀社や寺院の連絡先、予算の目安
- 事前に契約しているサービス
財産・契約の情報の整理
財産について、エンディングノートにまとめておくことで、相続手続きが円滑に進みます。
さらに、支払い関係の内容なども簡単にまとめておくと、整理や解約がスムーズになります。50代のうちに見直しておくことで、これからの生活にも良い影響があります。
- 預貯金や不動産、保険、株、不動産などの財産
- 遺言書の所在
- 特定の人や団体への寄付を希望しているか
- クレジットカード、公共料金、サブスクなどの解約が必要な契約
- 誰に知らせて、どう処理してもらいたいか
デジタル遺産も忘れずに
デジタル資産の管理もエンディングノートの重要な項目です。スマートフォンやパソコンのロック解除情報もあわせて記録しておきましょう。
- スマホ、PC、SNS、メール、クラウドサービス、ネット銀行のアカウントやID/PW
- 写真や思い出のデータをどう残したいか
- アカウント名やパスワード、管理や削除の希望
ペットや身の回りのこと

ペットを飼っている場合は安心して引き継いでもらえうために以下の情報を記載しておきます。
- ペットの世話をお願いしたい相手
- 性格や食事など生活習慣のメモ
- かかりつけの動物病院
また、思い出の品や遺品の整理についての希望を記録しておくことが受け取る人への思いやりになります。
- 住まいや家具、持ち物の整理・処分の方針
- 大切にしているものの行き先(形見、寄付、廃棄)
さらに伝えたい想いも自分の言葉で残しておくことができます。
- 「自分らしい生き方」「大切にしてきたこと」をどう残したいか
- 感謝の気持ちを伝えたい人はいるか
- 伝えたいメッセージや手紙、思い出に残したい言葉
最後に、信頼できる友人や専門職、施設の担当者など、必要な人にエンディングノートの所在を伝えておきましょう。
エンディングノート作り方のコツ
エンディングノートは、一度にすべてを書き終える必要はありません。自分のタイミングで、気負わずに始めることが大切です。書きやすい内容から手作りで少しずつ進めることで、気づけば「自分らしいノート」が自然と形になっていきます。
書けるところから気軽に
エンディングノートの作り方でおすすめなのは、「今書けること」からスタートする方法です。たとえば、自分の名前や連絡先など、事実ベースで書ける情報は書きやすく、最初の一歩にぴったりです。形式や順番にとらわれず、まずは思いついたこと、書きたいことを自由に書き出すことで、心のハードルがぐっと下がります。
定期的な見直しを
エンディングノートは、一度書いて終わりではなく、人生の変化に合わせて内容を更新していくものです。引っ越しや転職、健康状態の変化など、ライフイベントのタイミングで見直すと、情報が常に最新の状態に保てます。1年に1度、誕生日や年末など、定期的なチェック日を決めておくのもおすすめです。手作りのノートなら、バインダー式やデジタルツールを使うことで、項目の修正や追加も手軽にできます。
書かない項目があっても大丈夫
エンディングノートは、すべての項目を埋める必要はありません。まだ考えがまとまっていないことや、今は書きたくない内容は「未記入」や「あとで検討」と記しておくだけで十分です。
手作りで自由に作れるからこそ、自分に合ったペースでゆっくり進めることができます。必要だと感じたときに、何度でも追加や見直しができるのがエンディングノートの良いところです。
手作り以外の方法も検討してみよう|自分に合ったエンディングノートを見つけるために
手作りで自由に書き進める作り方も素晴らしいですが、最近では市販品や無料テンプレート、デジタル版など多彩な選択肢があります。それぞれに良い点があるので、自分のスタイルに合った方法を見つけることが出来ます。
書きやすさで選ぶなら市販のエンディングノート
書店や文具店、通販で手に入る市販のエンディングノートは、デザインや構成が工夫されたたくさんの種類が販売されています。たとえば、医療・介護・葬儀・相続などの項目が整理されている「もしもの時に役立つノート(コクヨ)」のような冊子タイプは、必要な内容を一通り押さえておけるので初心者にも安心です。身近なところで100円ショップにも「もしもノート」として販売されています。今すぐ始められる気軽さがポイントです。書くのが苦手な人にも使いやすく作られたものが多数あります。
気軽に始めたいなら無料テンプレートやPDFを活用
インターネットの環境がある方には、市区町村や葬儀社、終活セミナーなどが配布しているエンディングノートのテンプレートもおすすめです。費用をかけずにすぐ始められます。
インターネット上からPDFをダウンロードして、印刷して書き込めば、まさに手作りに近い感覚で活用できます。自分で項目を追加したり、必要に応じて整理し直したりできる柔軟さも特徴です。
デジタル派にはアプリやクラウド型のエンディングノートも便利
スマートフォンやパソコンに慣れている方には、アプリやクラウドサービスを使ったエンディングノートもおすすめです。
たとえば「エターナルメッセージ」のようなアプリでは、データを保存しながら必要なときに共有でき、内容の見直しも手軽に行えます。パスワード管理やバックアップ機能があるサービスもあるため、情報の安全性を保ちつつ、自分の意思をしっかり記録できます。
自分の性格やライフルタイルに会った方法を選ぶことで、無理なく、楽しくノートを作ることができます。途中で形を変えてもいいので、まず気になったやり方で始めてみることをおすすめします。
おわりに。。

わたしの父の死は突然でした。
コロナウィルスで入院し、そのまま退院することはありませんでした。延命や臓器提供の希望、葬儀やお墓・納骨の希望も一切なにも聞くことができませんでした。わたし達子供たちや孫、周りの人に伝えたかった言葉や渡したかったものがあったのかもしれないけれど、もうその声を聞くことはできません。
父の死がエンディングノートを作ろうと思ったきっかけでしたが、エンディングノートを書き進めていくうちに、自分の心の中の漠然とした将来の不安が整理されていくことに気づいたのです。そして、エンディングが決まると、それに向けて今すること、今起こす行動がはっきり見えてきました。
それはこれからをどう生きるか、自分自身と向き合い、大切に過ごすための道しるべになっています。
そして同時に、いつかそのノートを手に取る誰かへの、深い優しさと配慮にもつながります。手作りの一冊は、あなた自身と、あなたと大切な人たちの心をつなぐ、何よりも尊い一冊になるでしょう。
ありがとうございました。


